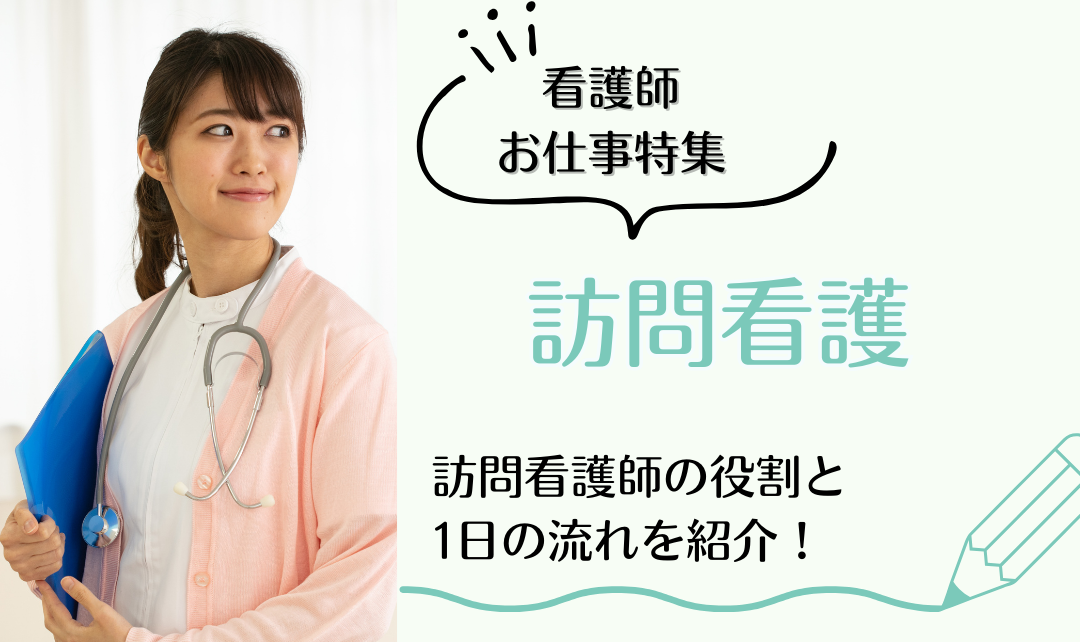酒井 隆之

本記事では、訪問看護ステーションの経営において重要な「訪問看護ベースアップ評価料」について詳しく解説します。ベースアップ評価料の概要や新設の背景から、算定要件の詳細、届出手続きの方法まで幅広く網羅。さらに、実務で役立つ計算支援ツールの活用方法や具体的な成功事例も紹介します。訪問看護ステーションの管理者や経営者の方々が賃金改善を効果的に実施するための実践的な情報をお届けします。
Contents
訪問看護ベースアップ評価料とは
訪問看護ベースアップ評価料について、その基本的な概要と新設された背景・目的を解説します。この制度を理解することで、訪問看護ステーションの賃金体系改善に役立てることができます。
医療制度の改革において重要な位置づけとなるこの評価料は、在宅医療サービスの質の向上と安定的な提供体制の構築に寄与するものです。また、訪問看護に従事する専門職の処遇改善を通じて、地域包括ケアシステムの中核を担う訪問看護の基盤強化にも貢献します。
ベースアップ評価料の導入は、持続可能な訪問看護サービス提供体制の確立という観点からも注目されており、多くの訪問看護ステーションにとって重要な経営課題となっています。
訪問看護ベースアップ評価料の概要
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションに勤務する医療従事者の賃金改善を目的として、2024年度の診療報酬改定で新設された評価料です。この制度では、訪問看護ステーションが一定の要件を満たして届出を行うことで、訪問看護基本療養費や訪問看護管理療養費とは別に、新たな評価料を算定することができます。
具体的には、看護師や理学療法士などの訪問看護に従事する職員の基本給や手当等の賃金改善に充てることを前提として、訪問看護の提供回数に応じて算定される仕組みとなっています。この制度により、訪問看護ステーションは継続的かつ安定的な賃金改善を実施することが可能になりました。
新設の背景と目的
この評価料は、医療従事者の処遇改善を図るために設けられ、特に訪問看護分野での人材確保とサービス向上を目的としています。近年、高齢化の進展に伴い在宅医療のニーズが高まる中、訪問看護の重要性はますます増大しています。
しかし、訪問看護分野では慢性的な人材不足が課題となっており、その要因の一つとして賃金水準の問題が指摘されてきました。このような背景から、政府は医療・介護職の処遇改善策の一環として、訪問看護分野における賃金改善の取り組みを推進することとなりました。
ベースアップ評価料の新設により、訪問看護ステーションは職員の基本給等の引き上げを行いやすくなり、結果として人材確保や定着率の向上、サービスの質的向上につながることが期待されています。
訪問看護ベースアップ評価料の種類と算定要件

訪問看護ベースアップ評価料には、(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があります。それぞれ異なる算定要件が設定されており、訪問看護ステーションの状況に応じて選択することができます。ここでは、各評価料の詳細な算定要件について解説します。
ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定要件
ベースアップ評価料(Ⅰ)は、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションが、医療従事者の賃金改善を図る体制にある場合に算定できます。主な算定要件は以下の表にまとめました。
| 要件項目 | 内容 |
| 対象施設 | 地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーション |
| 対象職員 | 訪問看護に従事する看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など |
| 賃金改善の形態 | 基本給や手当など毎月支払われる金額の引き上げが基本 |
| 必要書類 | 賃金改善計画書の作成・提出 |
| 報告義務 | 年度終了後の実績報告書提出が必要 |
| 改善継続性 | 算定期間中は継続して賃金改善を実施すること |
賃金改善は基本給や手当など毎月支払われる金額の引き上げが基本となり、一時金や賞与の増額のみの対応では要件を満たしません。また、算定期間中は継続して賃金改善を実施することが求められます。
ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定要件
ベースアップ評価料(Ⅱ)は、(Ⅰ)を算定している訪問看護ステーションが、さらに賃金改善を強化する場合に算定可能です。以下の表に主な算定要件をまとめました。
| 要件項目 | 内容 |
| 前提条件 | ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定要件をすべて満たしていること |
| 賃金改善水準 | (Ⅰ)で定められた基準額を上回る賃金改善を計画・実施すること |
| 対象範囲 | 賃金改善の対象職種や範囲を拡大することが望ましい |
| 人材育成 | 職員の技能向上やキャリア形成を支援する取り組みを行っていること |
| 実績報告 | より詳細な賃金改善実績の報告が求められる |
| 継続性 | より長期的・計画的な賃金改善の取り組みが求められる |
ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定により、訪問看護ステーションはより充実した賃金改善を実施することができます。また、単なる賃金アップだけでなく、訪問看護サービスの質的向上につながる人材育成の視点も重視されています。
届出の手続きと必要書類
訪問看護ベースアップ評価料を算定するためには、適切な届出手続きを行うことが必要不可欠です。ここでは、届出に必要な様式とその記載方法、および提出方法と期限について詳しく解説します。
正確な書類作成と期限内の提出により、スムーズに評価料の算定を開始することができます。届出手続きの流れを理解し、漏れなく対応することが重要です。
届出様式と記載上の注意点
届出には、厚生労働省が提供する専用の様式を使用し、記載上の注意点を遵守する必要があります。届出様式は主に「訪問看護ベースアップ評価料に係る届出書」と「賃金改善計画書」の2種類で構成されています。
届出書には、訪問看護ステーションの基本情報(名称、所在地、開設者名等)のほか、算定を希望する評価料の種類(Ⅰ/Ⅱ)や算定開始予定日を記載します。また、賃金改善計画書には、対象となる職員の範囲、賃金改善の具体的内容、改善見込額などを明記します。
記載にあたっては、数値の整合性に特に注意が必要です。例えば、職員数と賃金改善総額の関係性や、改善前後の給与水準の妥当性などが審査の対象となります。また、押印漏れや記入漏れがないよう、提出前の再確認が重要です。
届出の提出方法と期限
届出は、訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所の専用メールアドレスに提出します。新型コロナウイルス感染症の影響により、原則としてオンラインでの提出が推奨されています。
届出の期限については、算定開始希望月の前月15日までに提出する必要があります。例えば、7月から算定を開始したい場合は、6月15日までに届出を完了させなければなりません。期限を過ぎると、希望月からの算定開始ができなくなるため注意が必要です。
また、年度途中での届出も可能ですが、年度内の任意の月からの算定となります。届出内容に変更が生じた場合は、変更届も同様の方法で提出する必要があります。不備がある場合は差し戻しとなるため、十分な時間的余裕をもって準備することをお勧めします。
計算支援ツールの活用方法

訪問看護ベースアップ評価料の算定にあたり、正確な賃金改善計画の作成は重要なステップです。しかし、複雑な計算や様々な要件を満たした計画を立てることは容易ではありません。そこで役立つのが計算支援ツールです。
ここでは、厚生労働省が提供する計算支援ツールの概要と具体的な使用手順について解説します。このツールを効果的に活用することで、適切な賃金改善計画を効率的に作成することができます。
計算支援ツールの概要
厚生労働省は、賃金改善の具体的な計画を立てる際に役立つ計算支援ツールを提供しています。このツールはExcel形式で作成されており、訪問看護ステーションの規模や現状の賃金体系に応じた賃金改善計画を自動的に試算する機能を備えています。
計算支援ツールの主な特徴としては、職種別・職員別の賃金改善額の自動計算機能や、ベースアップ評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方に対応した試算機能などが挙げられます。また、賃金改善実施後の収支シミュレーション機能も搭載されており、経営面での影響も事前に確認することが可能です。
さらに、届出書類の作成支援機能も備えており、入力したデータをもとに必要な届出書類の一部を自動生成することができます。これにより、書類作成の労力を大幅に削減でき、記載ミスなども防止できます。
具体的な使用手順
ツールをダウンロードし、訪問看護ステーションの現状の給与総額や職員数を入力することで、賃金改善計画の試算が可能です。以下に具体的な使用手順を示します。
- 厚生労働省のウェブサイトから計算支援ツール(Excel形式)をダウンロードします。
- ツールを開き、「基本情報入力シート」に訪問看護ステーションの名称、所在地、開設者名などの基本情報を入力します。
- 「職員情報シート」に、現在雇用している職員の職種、雇用形態、現在の給与額などの情報を入力します。
- 「訪問実績シート」に、過去6ヶ月間の訪問看護の実績数を入力します。
- 「賃金改善計画シート」で、希望する評価料の種類(Ⅰ/Ⅱ)を選択し、職員ごとの賃金改善額を入力します。
- 自動計算された結果を確認し、必要に応じて調整を行います。
- 最終的な計画が確定したら、「届出書出力」ボタンをクリックして、届出に必要な書類を出力します。
- 出力された書類を確認し、必要に応じて修正や追記を行った上で、届出の準備を完了させます。
訪問看護ベースアップ評価料の活用事例
ベースアップ評価料の制度は、すでに多くの訪問看護ステーションで活用され、実際の成果を上げています。ここでは、実際にこの制度を導入して成功した事例と、賃金改善によってもたらされた具体的な効果について紹介します。これらの事例は、これから制度の活用を検討している訪問看護ステーションにとって、参考になる情報となるでしょう。
成功事例の紹介
実際にベースアップ評価料を活用して賃金改善を行った訪問看護ステーションの事例を紹介します。
■ Aステーションの事例
A訪問看護ステーションでは、ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定し、常勤看護師の基本給を平均5%引き上げることに成功しました。具体的には、勤続年数に応じた昇給テーブルを見直し、特に若手看護師の基本給底上げを重点的に実施しています。
■ Bステーションの事例
B訪問看護ステーションでは、ベースアップ評価料(Ⅱ)を取得し、夜間・休日の対応手当を従来の1.5倍に引き上げました。これにより、従来手薄だった時間帯のシフト調整がスムーズになり、利用者への24時間対応体制が強化されました。
■ Cステーションの事例
C訪問看護ステーションの事例では、理学療法士や作業療法士など、リハビリ専門職の処遇改善に特化した取り組みを実施。専門性に応じた資格手当の新設により、多職種連携の強化とサービスの質向上を両立させています。
賃金改善の具体的な効果
賃金改善により、職員のモチベーション向上や離職率の低下など、具体的な効果が報告されています。ある中規模訪問看護ステーションでは、ベースアップ評価料導入後の1年間で看護師の離職率が15%から7%に半減しました。特に、3年未満の若手看護師の定着率が大幅に向上しています。
また、賃金改善に加えて教育・研修体制を充実させたステーションでは、職員の資格取得率が向上。専門・認定看護師の資格取得者が増加し、サービスの質的向上にもつながっています。
経営面では、職員の定着率向上によって採用・教育コストが削減され、安定した経営基盤の構築に寄与している事例も見られます。さらに、職員満足度の向上が利用者満足度の向上にも波及し、新規利用者の増加や紹介率の向上といった好循環を生み出しているステーションも少なくありません。
このように、訪問看護ベースアップ評価料の活用は、単なる賃金アップにとどまらず、組織全体の活性化と持続的な成長につながる重要な取り組みとなっています。
まとめ
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションに勤務する医療従事者の賃金改善を支援する重要な制度です。評価料(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があり、それぞれの算定要件に沿った届出手続きを行うことで、持続的な賃金改善が可能になります。
計算支援ツールを活用すれば、効率的に賃金改善計画を立てることができ、実際の活用事例からは職員のモチベーション向上や離職率低下などの効果が報告されています。訪問看護の質の向上と人材確保のために、ぜひこの制度を有効活用しましょう。
著者プロフィール
酒井 隆之 株式会社アクタガワHRM コンサルタント