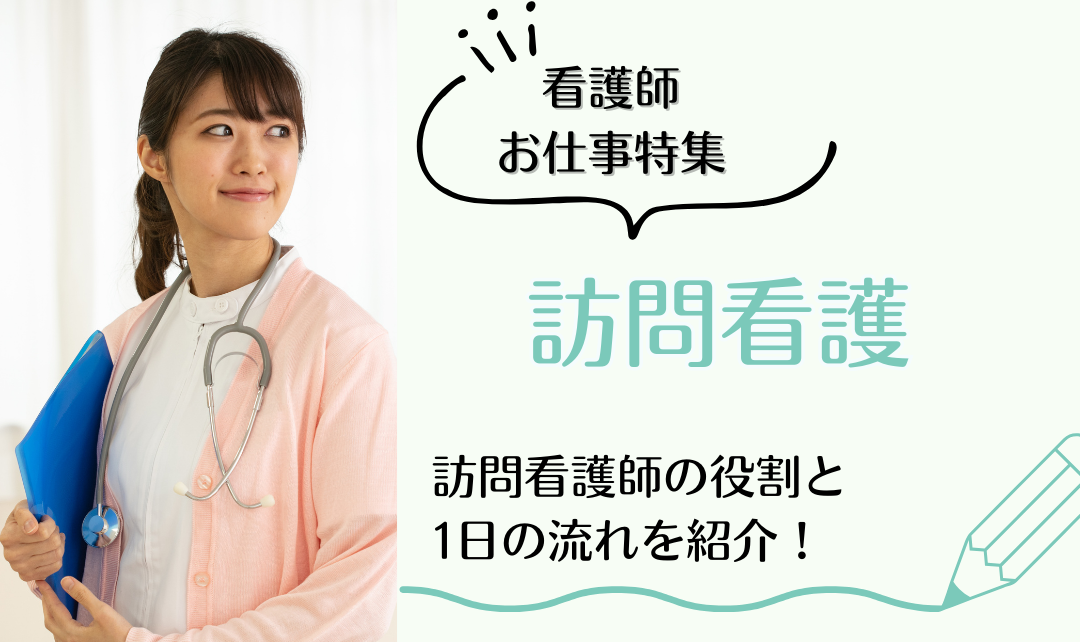訪問看護サービスにおいて、緊急時の対応は患者様の安全を守る重要な役割を担っています。そのため、介護保険制度では「緊急時訪問看護加算」が設けられています。この記事では、訪問看護における緊急時訪問看護加算の概要や種類、算定要件、請求手順などを詳しく解説します。
加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いや、24時間対応体制加算との比較、医療保険との違いなど、実務に役立つ情報も含めて解説していきます。訪問看護に携わる医療事務担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
訪問看護における緊急時訪問看護加算とは

訪問看護における緊急時訪問看護加算は、利用者やその家族からの緊急連絡や訪問要請に対して、24時間365日対応できる体制を整えている訪問看護ステーションに対して算定される加算です。
在宅で療養する要介護者の状態は常に変化する可能性があり、急な発熱や容態悪化など予期せぬ事態に迅速に対応できる体制の確保は、利用者とその家族に大きな安心感を提供します。この加算制度は、そうした緊急時対応の体制を評価し、質の高い訪問看護サービスの提供を促進するものです。
緊急時訪問看護加算の種類と単位数
緊急時訪問看護加算は、「緊急時訪問看護加算(Ⅰ)」と「緊急時訪問看護加算(Ⅱ)」の2種類に分けられています。これらの加算は、訪問看護ステーションが提供する緊急時対応サービスの内容や対象となる利用者の状態によって使い分けられ、それぞれ算定できる単位数も異なります。
介護報酬の請求において、適切な加算を選択することが医療事務担当者には求められます。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の概要
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、指定訪問看護ステーションが算定する場合、月に600単位が加算されます。この加算は、利用者やその家族からの電話等による緊急連絡に対して、常時(24時間365日)対応できる体制を整備していることを評価するものです。
具体的には、利用者の容態急変時や看護に関する相談に応じ、必要に応じて訪問看護を実施する体制を整えていることが求められます。また、緊急時には主治医や居宅介護支援事業者との連携も必要となります。この加算は月単位での算定となり、実際に緊急訪問を行ったかどうかにかかわらず、体制を整備していることに対して評価されます。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は主に特別管理加算を算定している利用者に適用されることが多く、医療依存度の高い利用者を対象としています。例えば、人工呼吸器や中心静脈栄養等を使用している方、末期の悪性腫瘍の方、褥瘡のある方などが対象となります。これらの利用者は状態が急変するリスクが高いため、迅速な対応が可能な体制が特に重要です。また、この加算を算定するためには、看護職員の労働負担に配慮した体制整備も必要とされており、夜間対応後の休息時間確保などの条件も含まれています。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の概要
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)は、指定訪問看護ステーションが算定する場合、月に574単位が算定されます。この加算も(Ⅰ)と同様に、利用者やその家族からの緊急時の連絡に常時対応できる体制を評価するものですが、主に特別管理加算を算定していない利用者を対象としています。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)とは単位数が異なり、また算定要件にも若干の違いがあります。(Ⅱ)は、医療ニーズが比較的低い利用者に対する緊急時対応体制を評価するもので、医療依存度の高い利用者向けの(Ⅰ)と区別されています。医療事務担当者は、利用者の状態や特別管理加算の算定状況に応じて、適切な加算を選択する必要があります。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の対象となる利用者は、例えば軽度の疾患を持つ高齢者や、状態が比較的安定している慢性疾患の方などが含まれます。これらの利用者は突発的な状態変化のリスクは(Ⅰ)の対象者と比べて低いものの、やはり緊急時の対応体制は重要です。
また、加算(Ⅱ)の算定には、基本的な緊急時対応体制の整備は必要ですが、(Ⅰ)で求められるような看護職員の労働負担軽減策などの追加要件は緩和されています。訪問看護ステーションは利用者の状態を適切に評価し、(Ⅰ)と(Ⅱ)を使い分けることで、効率的なサービス提供と適正な報酬請求を行うことができます。
緊急時訪問看護加算の算定要件

緊急時訪問看護加算を算定するためには、共通の基本要件と各加算種類に応じた追加要件を満たす必要があります。医療事務担当者は、これらの要件を正確に理解し、適切な算定を行うことが求められます。以下では、共通の算定要件と各加算特有の追加要件について詳しく解説します。
共通の算定要件
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)に共通する算定要件として、まず利用者やその家族等からの電話等による連絡に対し、24時間365日対応可能な連絡体制を確保していることが必要です。また、計画的な訪問以外にも必要に応じて緊急時訪問が可能な体制を整えていなければなりません。
さらに、サービス提供開始時に利用者に対して、緊急時の対応方法や連絡先を文書で説明し、同意を得ることが求められます。加えて、緊急時訪問看護を行う旨を都道府県知事に届け出ていることも算定の条件となります。
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の追加要件
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)を算定するには、共通要件に加えて、看護職員の負担軽減に資する体制整備が求められます。具体的には、夜間・早朝の訪問看護対応後、看護職員に十分な休息時間(訪問終了後から次の勤務開始までに少なくとも11時間)を確保することが必要です。
また、看護職員の連続勤務回数の上限設定(例えば連続して5回まで)や、夜間・早朝の対応後に休日が確保できる勤務スケジュール管理も求められます。これらの条件は、看護職員の過重労働を防ぎ、質の高い訪問看護サービスを安定的に提供するために設けられています。
この追加要件は、令和3年度の介護報酬改定で新たに設けられたもので、看護職員の働き方改革を推進する観点から導入されました。実務上は、訪問看護ステーションは勤務表や業務記録などによって、これらの要件を満たしていることを証明できる体制を整えておく必要があります。
緊急時の対応手順を明確化し、マニュアルを整備することも重要です。具体的には、緊急連絡を受けた際の対応フローチャートの作成、看護職員間の連携体制の確立、緊急時に関する情報共有の仕組みづくりなどが含まれます。これらは書面化して、全スタッフが常に確認できる状態にしておくことが望ましいでしょう。
さらに、定期的な研修や訓練を実施することで、実際の緊急時にスムーズに対応できる体制を維持することも推奨されています。
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の追加要件
緊急時訪問看護加算(Ⅱ)の場合、主に共通要件を満たすことが算定条件となり、(Ⅰ)で求められるような看護職員の負担軽減策に関する追加要件は必須とはなっていません。基本的に24時間対応可能な連絡体制の確保と、緊急時訪問が可能な体制の整備、利用者からの同意取得、都道府県知事への届出が主な要件です。
(Ⅱ)は、特別管理加算を算定していない利用者を対象としており、比較的医療ニーズが低い利用者に対する緊急時対応体制を評価するものであるため、要件も(Ⅰ)と比較するとやや緩和されています。医療事務担当者は、利用者の状態に応じて適切な加算を選択することが重要です。
ただし、共通要件を満たすためには、以下のような具体的な体制整備が必要となります。まず、緊急連絡を受けるための専用電話や携帯電話を設置し、その番号を利用者に明示することが求められます。また、緊急連絡を受けた際の対応手順を明確化し、必要に応じて訪問するための人員配置や移動手段の確保も必要です。
さらに、訪問看護計画書には緊急時の対応方法を具体的に記載し、利用者や家族に説明して同意を得ることが重要です。この計画書には、緊急時の連絡先(主治医や家族、ケアマネジャーなど)も明記しておくと良いでしょう。また、実際に緊急連絡があった場合は、その内容や対応結果を訪問看護記録書に詳細に記録し、適切に保管することも求められます。こうした記録は、算定の根拠資料となるだけでなく、サービスの質向上にも役立ちます。
緊急時訪問看護加算の請求手順と注意点

緊急時訪問看護加算を適切に請求するには、所定の手続きを正確に理解し、漏れなく進めることが重要です。算定要件を満たしていても、手続きや記録に不備があると、請求が認められない場合があります。ここでは、医療事務担当者が知っておくべき請求の流れと実務上の注意点について詳しく解説します。
請求手順の概要
緊急時訪問看護加算の請求手順は以下のステップで進めます。
- 利用者からの同意取得
- 緊急時対応についての説明を書面で行い、同意書に署名をもらう
- 同意書には緊急時の連絡先や対応方法を明記する
- 体制整備と届出
- 24時間対応が可能な体制を整備する
- 所定の様式を用いて都道府県知事に届出を行う
- 届出には緊急時対応が可能な看護師の配置状況などを記載する
- サービス提供と記録管理
- 訪問看護計画書に緊急時の対応方法を記載する
- 緊急連絡があった場合は、対応内容を詳細に記録する
- 訪問看護記録書とともに緊急時の対応記録を適切に管理する
- 請求手続き
- 月単位で加算を算定する
- サービス提供月の翌月に請求を行う
- 介護給付費請求書および介護給付費明細書に必要事項を記入する
注意すべきポイント
緊急時訪問看護加算の請求において、特に注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 24時間対応体制が形式的なものではなく、実際に機能していることを示す記録が必要
- 緊急連絡を受けた場合の対応記録を残し、日時、内容、対応者、対応内容を明確に記載
- 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の算定要件の違いを理解し、利用者ごとに適切な加算を選択
- 特別管理加算を算定している利用者には、通常は加算(Ⅰ)が適用される
- 緊急時の訪問については、通常の訪問看護と別に緊急時訪問看護として記録して請求
- 利用者が入院した場合は、その月の加算は日割り計算ではなく、月額での算定が原則となる
- 月の途中で加算の算定を開始する場合も、日割りではなく月額での算定となる
緊急時訪問看護加算と他の加算との違い
訪問看護サービスには、様々な加算制度が存在します。特に「緊急時訪問看護加算」は、名称や内容が類似した他の加算と混同されやすい傾向があります。
ここでは、緊急時訪問看護加算と似た性質を持つ他の加算との違いを比較しながら、それぞれの特徴を整理します。医療事務担当者として、これらの違いを正確に理解することで、適切な算定が可能になります。
24時間対応体制加算との比較
24時間対応体制加算は、利用者やその家族からの連絡に対して「対応できる体制」を評価する加算であり、実際に緊急訪問を行ったかどうかは問われません。電話等による連絡体制が整備されていることが主な要件となります。一般的に月額574単位で算定されます。
一方、緊急時訪問看護加算は、連絡体制に加えて、実際に訪問して対応できる体制の整備が求められます。特に加算(Ⅰ)では、看護職員の負担軽減策も要件に含まれており、より実働に近い体制整備が必要です。また、単位数も緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は600単位、(Ⅱ)は574単位と、24時間対応体制加算とは異なります。
両者は似た名称ですが、体制の整備レベルや算定要件に違いがあるため、混同しないように注意が必要です。
医療保険における緊急訪問看護加算との違い
医療保険制度の訪問看護療養費には「緊急訪問看護加算」が存在します。これは、計画外の緊急訪問を実際に行った場合に、その都度算定できる加算です。具体的には、利用者の状態急変等に伴い、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に訪問した場合、1日につき1回2,650円が加算されます。
一方、介護保険における「緊急時訪問看護加算」は、実際の訪問の有無にかかわらず、緊急時に対応できる体制を整備していることに対して月単位で算定される加算です。医療保険の加算が「実績払い」であるのに対し、介護保険の加算は「体制評価」という性格の違いがあります。
医療事務担当者は、医療保険と介護保険の違いを理解した上で、適切な制度を適用することが重要です。医療依存度の高い利用者の場合、両方の制度を併用することもあるため、混同しないよう注意が必要です。
まとめ
訪問看護における緊急時訪問看護加算は、24時間365日の緊急対応体制を評価する重要な加算制度です。加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2種類があり、それぞれ算定要件や単位数が異なります。適切に請求するためには、共通の算定要件と各加算特有の追加要件を理解し、正確な手続きを行うことが重要です。
また、24時間対応体制加算や医療保険の緊急訪問看護加算など、類似した加算との違いも把握しておくことで、より適切な訪問看護サービスの提供と請求が可能になります。
監修者プロフィール
東海林 さおり(看護師) 株式会社アクタガワ 看護師スーパーバイザー

看護師資格修得後、病棟勤務・透析クリニック・精神科で『患者さん一人ひとりに寄り添う看護』の実践を心掛けてきた。また看護師長の経験を活かし現在はナーススーパーバイザーとして看護師からの相談や調整などの看護管理に取り組んでいる。